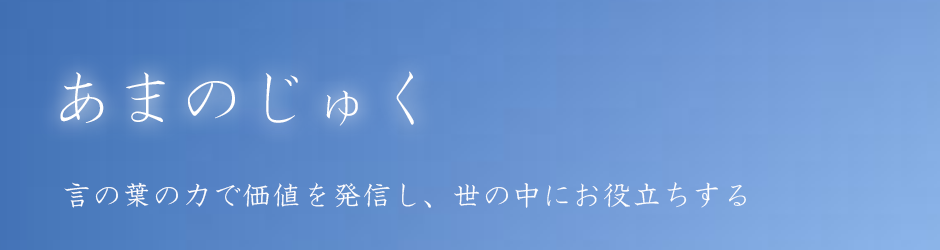〇 冒険商人フェルナン・メンデス・ピント
ポルトガル王ジョアン2世(在位1481-1495年)は、1492年スペインから追放されポルトガルに逃れてきた推定12万人のユダヤ人を受け入れた。王は、永住権を望む富裕なユダヤ人から多額の納付金を、また入国希望者全員から8か月という条件付きの滞在許可を認めて人頭税を徴収できると目論んだ。かくて移住者はみな、滞在許可を得るために、八(8)ドゥカーテン金貨を払わされた。
「これによって、喜望峰を周航し、インド航路を開拓し、ブラジルを発見して、ポルトガルを一大海運国に飛躍させる船舶の調達が可能になったのである。」(前掲書『マラーノの系譜』p. 19)
—
ジョアン2世の後を継いだ「幸運王」マヌエル1世(在位1495-1521年)はこれらスペインからのユダヤ人避難民に自由を与え、しかも王国のユダヤ人社会がこの寛大な処置に感謝して捧げた贈り物も受け取らなかったという。
マヌエル王は、将来自分の跡継ぎが統一されたイベリア半島を支配して欲しいと切に願い、スペインのカトリック両王(フェルナンドとイサベル)の娘イサベル王女に求婚した。それに対して、カトリック両王は彼らがスペインで行ったように、まずポルトガルからすべてのユダヤ教徒を追放するよう、マヌエルに要求した。マヌエルは苦しい立場に立たされた。というのも、マヌエルはイサベル王女との結婚を望んでいたが、一方で彼が当時建設しつつあった新しい貿易帝国のためにユダヤ人の商才を必要としていたからだ。
解決策として、マヌエルは(1496年に)ユダヤ人を正式にキリスト教に改宗させる手を打ちながらも、事実上、一世代30年間は異端審問から彼らの身を守ると約束した。実際、ポルトガルでは1536年まで異端審問所が設置されなかった。こうして少なくともマヌエル王の在位期間中は、ポルトガルのマラーノは社会に積極的に進出していきながら、宗教弾圧を受けることなく、秘密裡にユダヤ教を信仰することができた。
「ヴァスコ・ダ・ガマのインド航路発見(1498年)とペドロ・アルヴァレス・カブラルのブラジル発見(1500年)によって、マヌエル王治下のリスボンが、香辛料や砂糖、金などの世界的な貿易港となった16世紀初頭、ポルトガルのマラーノにも活路が開けてきた。それというのも、新航路発見までは東方貿易の活発な中継地点だった地中海東部沿岸地帯「レヴァント」の多くの港町に、1492年にスペインから追放されたセファルディ [スペイン系ユダヤ人] の従兄弟たちがすでに住みついていたので、ポルトガルのマラーノたちは彼らと血の繋がりによって直接結びつくことができたからである。」(本書p. 94-95)
「かくて、マラーノ出身の商人たちは、ヴェニスおよびジェノヴァの商人が中世全体を通じて独占していた東方貿易の大部分を奪い取ることに成功したのだった。
いまや、インドおよびブラジルなどから運ばれてくる数々の貴重品を扱う大型の貿易は、もっぱらマラーノ系商人の手にゆだねられ、しかも国際的な貿易の嘱目すべき活性化は、大部分リスボンのマラーノたちに負っていた。」(前掲書『マラーノの系譜』p.29)
マラーノは、国の内外で強い絆によって結ばれていた。彼らは情報と記号を持って、あらゆる境界を乗り越えて交通する漂泊の民であった。
だが、マヌエル1世の跡を継いだジョアン3世(在位1521-1557年)は、植民政策の拡大とともに著しく力をつけてきた新興の中間層マラーノを封じ込める必要性を痛感し、ついに1536年異端審問制度を導入する。
—
この時期にポルトガルから海外に出て活躍したマラーノ系の人物の一人に、冒険商人フェルナン・メンデス・ピントがいる。彼は、マラッカ、マカオ、ゴア、日本などを舞台に、ある時は商人あるいは海賊として、またある時はイエズス会士あるいは使節として、神出鬼没の活躍を見せた。
フェルナン・メンデス・ピントは、一説によれば、ポルトガルで「新キリスト教徒」(Cristâos Novos)とも、あるいはただ「商人」(homens de negócio)とも言われたマラーノの家系に属していたという。アメリカの文学史家レベッカ・カッツは、その著書《A sãtira social de Fernão Mendes Pinto》(Lisboa, 1978)の中で、ピントが16世紀のアントウェルペンで貿易商人として活躍した改宗ユダヤ人のメンデス家と血縁関係があると推測している。
—
フェルナン・メンデス・ピントは、1509年頃、ポルトガル中部の村モンテオル・オ・ヴェーリョに生まれた。貧しい生家の困苦窮乏の中で10歳ないし11歳まで過ごしたこの少年は、彼にもっと幸せな生活をさせてやろうと望んだ叔父によって、リスボンに連れて来られた。そこで彼は「非常に高貴な生まれの、たいそう立派な親戚をもつある婦人」の家に奉公することになったが、「この婦人に仕えて一年半経った時、ある事件が降りかかり、そのため危険に身を曝され、生命が助かるためには、その時その家をできる限り急いで逃げ出さざるを得なかった」と彼は書いている(『東洋遍歴記』、メンデス・ピント著、岡村多希子 訳、平凡社)。
本書著者の小岸氏は、この時ピントの身に降りかかった「ある事件」とは、ジョアン3世治下の旧キリスト教徒によるユダヤ人襲撃だったと推定している。新しい「闘う教会」の尖兵イエズス会士に心酔し、インドにおける宣教活動を推進したジョアン3世とそのスペイン生まれの妻カタリーナの治世において、ユダヤ人に対する憎悪が爆発していた。こうして、逃げ足の早いマラーノの持って生まれた才能を武器にして、1537年3月11日、メンデス・ピントは、五隻の船から成る艦隊に潜り込み、無一文のまま、物騒な本国ポルトガルを去って、インドに向かったのである。
—
1546年の秋口から初冬にかけてのある日、鹿児島湾山川の港に、ザビエルの友人のポルトガル人船長ジョルジェ・アルヴァレスの船が停泊していた。馬に乗った二人の男が、大声で自分たちを乗せてくれと叫びながら、大急ぎでやって来た。そのうちの一人の男は、大勢の者に追われているのだと言った。
この男が、後にザビエルを日本に案内することになるアンジロウであり、彼の話を聞いていたのが、冒険商人フェルナン・メンデス・ピントであった。
馬に乗った役人があわせて23人も浜に現れ、その裏切り者を寄越さないと殺すぞ、と脅しても、ピントは動ずることなく二人を伴って悠然と本船に帰った。
1548年11月29日付ゴア発イグナチオ・デ・ロヨラ宛アンジロウの書簡によれば、彼は日本にいる時、人を殺害してしまった。そのため某僧院に身を隠したが、ちょうどその頃港に停泊していた船に乗っているアルヴァロ・ヴァスというポルトガル商人と知り合った。この男は、目下インドにフランシスコ・ザビエルという聖徒がおり、彼ならばきっと大罪を犯した者であっても喜んで迎えてくれるだろうと教えてくれたうえに、別の港から出航しようとしている人物宛に紹介状まで書いてくれたのだという。そして、紹介された人物の船を探しているうちに、たまたま山川の港から出航しようとしている船長ジョルジェ・アルヴァレスと出会ったというわけだった。
アルヴァレスは、結局アンジロウの日本脱出を成功に導き、船上で彼にキリスト教教理の手ほどきをして、1547年12月7日にマラッカの「丘の聖母教会」でザビエルとアンジロウの出会いを実現させた。このザビエルとアンジロウの出会いが、ザビエル訪日の決定的引き金になったと見られている。この出会いを通して、インド布教に挫折していたザビエルが、この男(アンジロウ)の国でなら「神の国」を実現できるというひらめきを得たであろうことは、間違いない。
こうして、ジョルジェ・アルヴァレスを、ザビエルの日本開教のきっかけを作った最大の功労者とするのが定説だが、メンデス・ピントもこのザビエルとアンジロウの劇的な対面の場に居合わせていたのである。脇役にされた感のあるメンデス・ピントだが、彼はザビエル来日の影の立役者と言えるかもしれない。
—
1551年三度目の日本訪問の際、折しも布教に精励していたザビエルと親しく交わった冒険商人フェルナン・メンデス・ピントは、その著書『東洋遍歴記』の中で、ザビエルの臨終の様子を記している。ザビエルは中国への布教を目指し、中国へ渡ろうとしたが、それを目前にした上川(さんちゃん)島で最期を迎えた。ザビエルは最期に十字架を手に取り、それをじっと見つめながら、「こうして、ついにすっかり魂を神に渡したのであったが、それは1552年12月2日土曜日の真夜中のことだった」という。

—
フェルナン・メンデス・ピントの自伝的冒険小説『東洋遍歴記』は、マラーノが活躍する悪漢小説「ピカレスク・ロマン」の要素を多分に持っており、とりわけ二重言語の技巧を凝らした作品として見る必要がある。
悪漢小説「ピカレスク・ロマン」について、現代イスラエルの哲学者イルミヤフ・ヨベルは、「16世紀には、宗教上の懐疑主義や現実主義と並んで、悪漢小説『ピカレスク・ロマン』という特殊スペイン的ジャンルが生み出された。そこにおいては、改宗者の著者たちが一頭地を抜いていた。この新たなジャンルには、マラーノの状況を暗にほのめかす言葉が隠されている。この文学ジャンルはいつも決まって、曖昧な表現という技巧を凝らしている。」と述べている。(『スピノザ 異端の系譜』、イルミヤフ・ヨベル著、小岸昭/ E ・ヨリッセン / 細見和之 訳、人文書院、1998年)
(下のページ番号をクリックして、次のページへお進みください。)