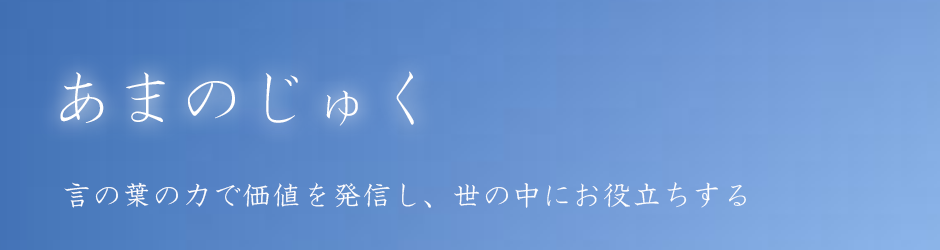民謡の「ドナドナ」が元々何語の歌か、ご存知でしょうか?
次の音源をお聴きください:
冒頭の問いの答えはイディッシュ語。イディッシュ語は、東ヨーロッパのユダヤ人が日常語にしていた言葉だ。発音と文法はドイツ語に近い。
上でお聴きいただいた音源は、ドイツのフォークグループ Zupfgeigenhansel (ツップフガイゲンハンゼル)の ”Jiddische Lieder”(『イディッシュの歌』)というレコード(CD)に収録されている ”Dos kelbl”(『子牛』)という曲。
イディッシュ語の歌詞とその翻訳を載せる。(なお、実際のイディッシュ語の表記は、ヘブライ文字を用いて右から左に綴っていくが、ここでは便宜上、アルファベットを用いて左から右に綴っている。)
| “Dos kelbl” | 「子牛」 |
| Ojfn forel ligt a kelbl, | 荷車のうえに子牛が一頭 |
| ligt gebundn mit a schtrik, | 縄に縛られて横たわっている |
| hojch in himl flit a fojgl, | 空高く一羽の鳥が舞っている |
| flit un drejt sich hin un ts’rik. | 鳥は行ったり来たりして飛びまわっている |
| * | * |
| Lacht der wind in korn, | ライ麦畑で風が笑う |
| lacht un lacht un lacht, | 笑って笑って笑い続ける |
| lacht er op a tog, a gantsn, | 一日中 |
| un a halbe nacht. | そして夜半まで |
| donaj, donaj, donaj, donaj | ドナイ・ドナイ・ドナイ・ドナイ |
| donaj, donaj, donaj-doj… | ドナイ・ドナイ・ドナイ・ダイ |
| Schrejt dos kelbl, sogt der pojer, | 子牛がうめくと農夫が言う |
| wer-ssche hejst dich sajn a kalb? | いったい誰が子牛であれとお前に命じたのか |
| Wolst gekent doch sajn a fojgl, | お前だって鳥であることができたろうに |
| wolst gekent doch sajn a schwalb. | 燕であることができたろうに |
| * 繰り返し | * 繰り返し |
| Bidne kelblech tut men bindn, | ひとびとは哀れな子牛を縛りあげ |
| un men schlept sej un men schecht. | そして引きずっていって殺す |
| Wer’s hot fligl, flit arojf tsu, | 翼を持つものなら空高く舞い上がり |
| is bei kejnem nischt kejn knecht. | 誰の奴隷にもなりはしない |
| * 繰り返し | * 繰り返し |
イディッシュ語の歌詞はCD版Zupfgeigenhansel ”Jiddische Lieder” (Verlag „pläne‟ GmbH, 1985)による。
翻訳は、細見和之 著『ポップミュージックで社会科』(みすず書房、2005年)による。
—
このレコードによると、曲のクレジットは、作詞者がイツハク・カツェネルソン、作曲者は不明となっている。細見和之氏の前掲書『ポップミュージックで社会科』によれば、このレコードには作詞者のカツェネルソンについて、次のようなドイツ語の解説が添えられているという。
「イツハク・カツェネルソン(1886-1944)は作家であり、ウーチ [注: ポーランドの工業都市] のユダヤ学校で教鞭をとっていた。彼は詩、戯曲、歌を書いた。彼の劇の多くはポーランド、ソ連、合衆国のイディッシュ劇場で上演された。戦争勃発後、彼はワルシャワに暮らし、ワルシャワ・ゲットーの地獄を体験した。彼はユダヤ人の闘争組織と密接なつながりをもっていた。1942年に彼の妻と11歳と14歳のふたりの息子が「移住」させられ、殺された。イツハク・カツェネルソンは、ワルシャワ・ゲットーから絶滅収容所アウシュヴィッツへのこの移送を思って、子牛の歌を書いた。家族と同様に彼もまた「移住」させられ、1944年4月、アウシュヴィッツで死んだ。」(翻訳は、前掲書『ポップミュージックで社会科』による。)
ここで「移住」とは、当時のナチの用語で、ユダヤ人たちをゲットーから絶滅収容所に運んでそこで殺すことを意味する。細見氏によれば、カツェネルソンの妻と二人の息子が「移住」させられたのは、実際にはアウシュヴィッツではなくトレブリンカの絶滅収容所だという。
なんと、「ドナドナ」は家族をホロコーストで失ったユダヤ人の哀しみを歌った歌だったのか?!
(ご参考情報として、イツハク・カツェネルソンにはイディッシュ語で著した『滅ぼされたユダヤの民の歌』という著作があり、同書は細見和之・飛鳥井雅友 両氏によって翻訳され、みすず書房から1999年に出版されている。)
(下のページ番号をクリックして、次のページへお進みください。)